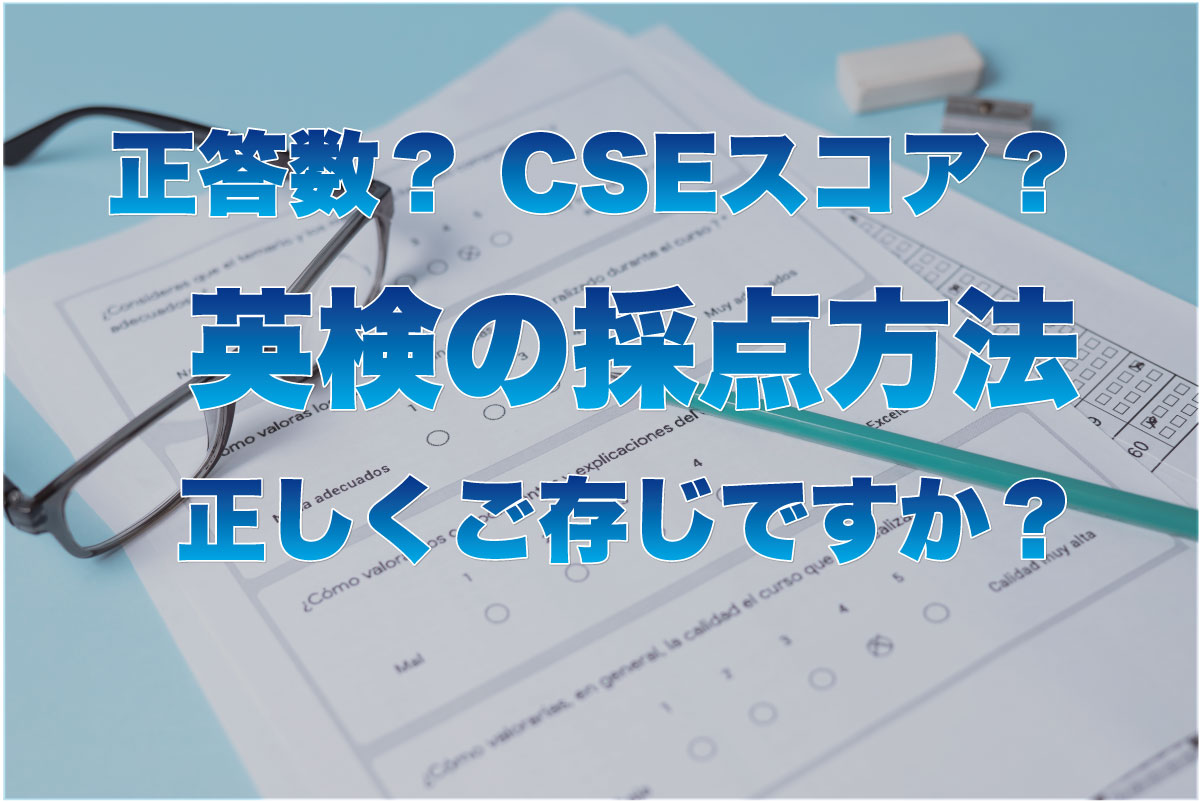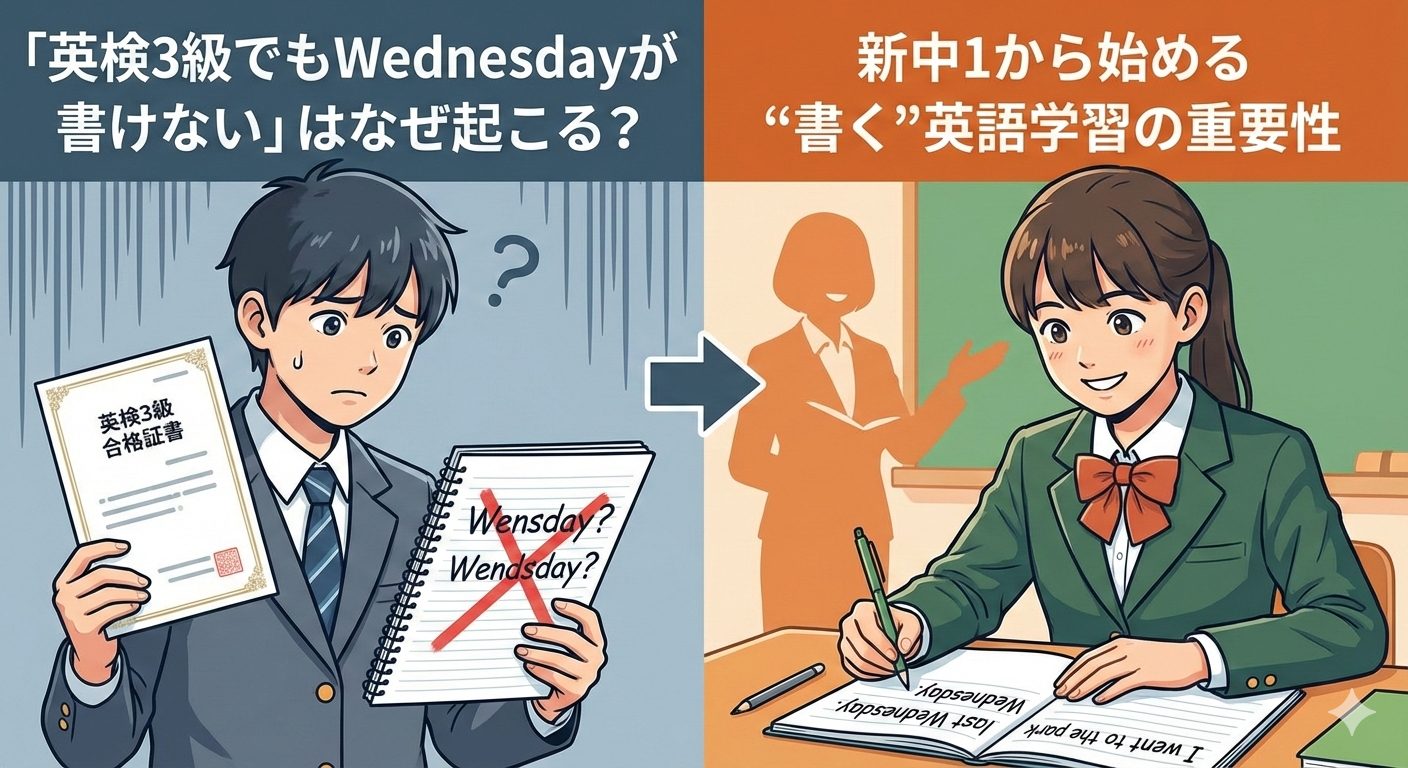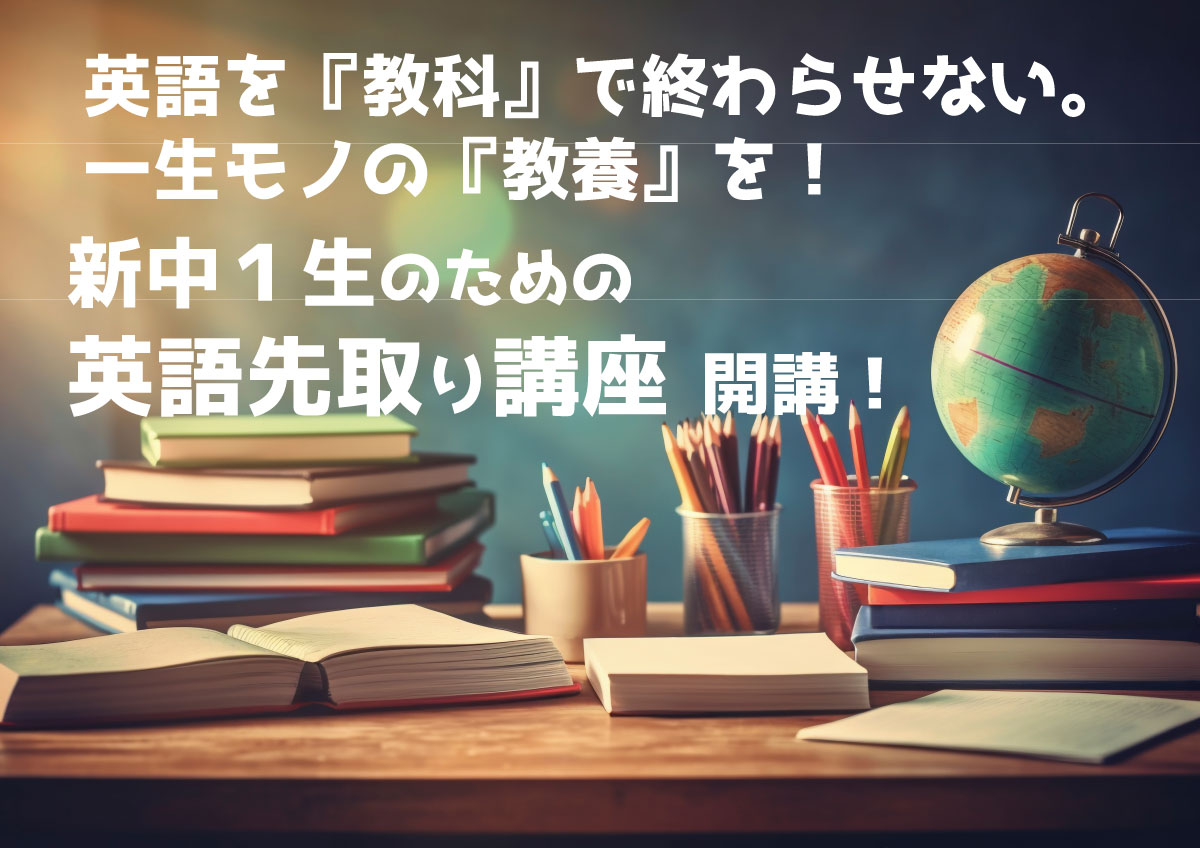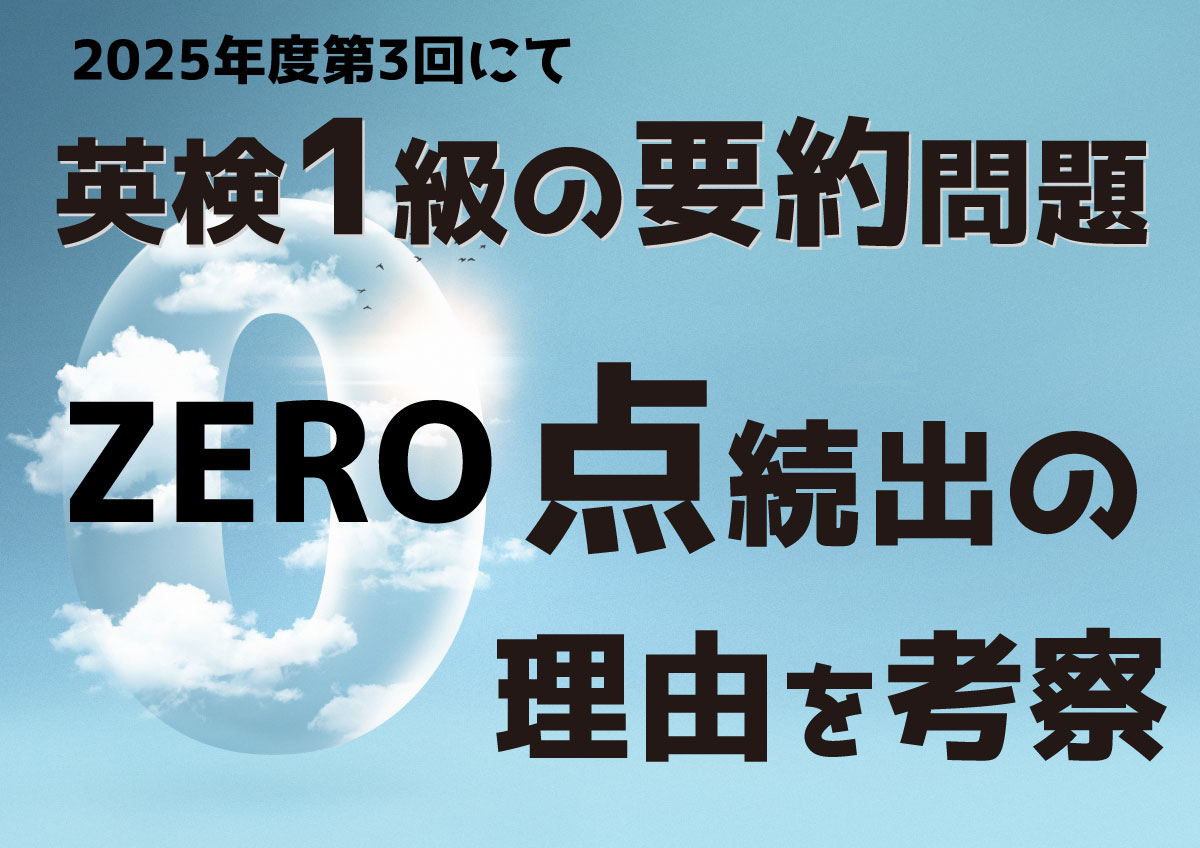
英検に新しい級「6級・7級」が生まれます!

英検6級・7級が新たに創設されます。今回は、これらの級が生まれた経緯とその存在意義について、考えてみたいと思います。
目次
― 英検の内容が時代に取り残される中で、級の追加は本当に必要? ―
2025年11月27日に公表されたプレスリリースで、英検協会は2026年度の第3回(2027年1月実施分)より「英検6級」「英検7級」を新設する方針を発表しました。英語学習初期の段階に対応するという狙いが述べられておりますが、教育現場に携わる立場としては、いくつかの点で疑問が残る印象です。
■基礎段階のさらなる細分化は必要なのか
現行の英検5級は中学1年生レベルとされていますが、そのさらに下位に級を設けることにどれほどの意味があるのか…。これが第一の疑問です。学習者のモチベーション向上につながる可能性がある一方、級の細分化によって体系が複雑になり、かえって受検者や保護者が何を受けたらいいのか迷う場面も増える懸念があります。また、すでに小学生を対象とした英検Jr.というテストが存在しているため、新設級との境界がやや分かりづらい印象があります。英語に親しむ段階を支える英検Jr.と、英語力を評価する英検のどこで線引きを行うのか、よくわかりません。実際英検ジュニアのゴールドレベルのリスニングは、5級よりも単語のレベルが高く、高難易度の問題も含まれています。
■学習指導要領とのズレが広がりつつある
さらに懸念される点として、英検がもともと旧来の学習指導要領に合わせて作られてきた検定であることが挙げられます。
現行の指導要領と比べると、いくつかの級で内容が追いついていない部分が見られます。あくまで、英検のレベル分けは中学初級、中級、卒業程度となっていますが、それぞれ中1、中2、中3をイメージして作られていることは明白です。
- 5級(中学初級程度)
5級では過去形は出題されませんが、現代の指導要領では中1段階で過去形、過去進行形、未来形までが習得範囲となっています。 - 4級(中学中級程度)
4級では、現在完了は出題されませんが、現代の指導要領では中2段階で、完了形が指導範囲になっています。 - 3級(中学卒業程度)
3級では仮定法は出題されませんが、現在の指導要領では中3段階で仮定法(仮定法過去のみ)が指導範囲になっています
このように、すでに英語学習初心者が受ける英検の級では、現場の学習内容との想定範囲にズレが生じているため、さらに下の6級・7級を創ったとして、何を基本に出題をするのか、どのレベルを想定しての設定なのかが、いまひとつ見えてきません。もちろん、まだ新級の設置が発表されただけで、その内容までが発表されたわけではないため、こういった意見は無意味かもしれません。もしかすると、英断で6級と7級は発音だけを重視して、英語の発音を問う問題にする、AIで採点を行う、などといった形であれば、非常に差別化が図られて面白いと思います。こういった点からも本来必要なのは各級の根本的な内容刷新や時代に合わせた再設計ではないか思います。
■近年の内容改革との整合性、時代の変化に追いついていけるのか
英検はここ数年、内容面で大きな変化を進めています。
昨年2024年からは上位級に要約問題の導入、今年は準2級プラスの新設が行われ、形式・評価方法ともにアップデートされてきました。こうした改革が進む中で、体系はそのままに級だけを追加することが、意味があるのかは疑問です。実際、英検はかつて『限定された英語力しか測れないテスト』という評価を受けています。実際当時準1級より下の級はライティングがなく、リスニング、リーディングだけであったことから、ライティングの導入にもつながりました。しかし今やリーディングで重視される短文・長文穴埋めや内容一致の問題形式は、語彙力重視にほかならず、正確にその人の英語力を測っているとは言いづらく、ライティングでは毎度のことながら、採点のクライテリアにムラがあります。そして「読む・書く」といった技能は、おそらく今後一番AIにとってかわられる技能になります。本来はより思考力を試すような問題、さらに今後は「聞く・話す」技能が一層重視される流れが続くと予想されるため、級の増設よりも、技能バランスや出題形式の再検討がより効果的なのではないかという印象を持っています。
■まとめ
6級・7級の新設には、新たな学習者層を支援する意義が含まれている可能性があります。一方で、現行体系との重複や、英検Jr.との境界、さらに学習指導要領との乖離、そもそもの英検の内容の見直しの必要性など、気になる点はたくさんあります。
何はともあれ、英検がブームになると必ず現れる、英検取得レースを過熱化させるようになるのは、避けたいことです。あくまで英検は現状の英語力の健康診断。「普段からの頑張りを試す機会」という位置づけは変わらずにあってほしいものです。